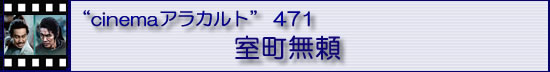こんにちは。気付けば人生の傍らには必ず映画があった岸波です。
たった一行の史実から生まれた、
戦国前夜の歴史的戦い。
今年1月に劇場公開された大泉洋主演の『室町無頼』が、早くもAmaプラで無料配信されたので視聴しました。
演じるのは室町中期の寛正3年(1462年)に起きた「寛正の土一揆」の指導者として名を遺す蓮田兵衛。
その前に立ちはだかるのは蓮田兵衛の悪友で、幕府の傭兵大将にまで上り詰めた骨皮道賢(堤真一)。しかぁしっ・・!!
道賢に拾われて兵衛に預けられ、やがて六尺棒術の達人として成長する才蔵(長尾謙杜:なにわ男子)こそが真の主人公に見えて来る造りになっています。
 土一揆での才蔵の無双シーンは圧巻! 土一揆での才蔵の無双シーンは圧巻!
原作は2016年の第6回「本屋が選ぶ時代小説大賞」を受賞した垣根涼介による同名の歴史小説。
 原作者:垣根涼介 原作者:垣根涼介
動乱の南北朝時代が後小松天皇によって両朝合一された1392年。そこから1462年の応仁の乱を契機として戦国時代に突入するまでの実質的には短い室町幕府の安定期。
しかし「安定」と呼べるのは政権中枢だけであり、世の中は、繰り返す大飢饉と疫病の流行で疲弊し、民を省みない為政者の圧政に苦しんでいました。
そこで、自らの出自が武家であったにも拘わらず民を扇動し、世直しに立ち上がったのが剣の達人蓮田兵衛だったのですね。(実在の人物:知らなかった・・)
さて、映画の内容はいかに?

世界を変えるのは、人の力。
映画の冒頭、人々が飢えと疫病に苦しむ中、放蕩な大名名和好臣(北村一輝)の個人的趣味のため、巨石を庭まで運ばされている人夫たち。

鴨川の河原では大量の死体が焼かれ、道端には行き倒れや物乞いたちで溢れている。そこに通りがかった蓮田兵衛(大泉洋)は、小役人らを死体の山の中に突き落として喝采を浴びる。
そして、道端に空腹でうずくまる母娘に懐から食べ物を渡し、自分の外套かけてやるとカメラが遠景に切り替わり『室町無頼』のタイトルが大写しになる。
 |
|
この後のあらすじと概略は以下のとおり。
◆『室町無頼』(2025年)のあらすじと概略 (映画.comより)
垣根涼介の時代小説を大泉洋主演で実写映画化した戦国アクション。「22年目の告白 私が殺人犯です」の入江悠が監督・脚本を手がけ、日本の歴史において初めて武士階級として一揆を起こした室町時代の人物・蓮田兵衛の知られざる戦いをドラマチックに描く。
1461年、応仁の乱前夜の京。大飢饉と疫病によって路上には無数の死体が積み重なり、人身売買や奴隷労働も横行していた。しかし時の権力者は無能で、享楽の日々を過ごすばかり。そんな中、己の腕と才覚だけで混沌の世を生きる自由人・蓮田兵衛はひそかに倒幕と世直しを画策し、立ち上がる時を狙っていた。一方、並外れた武術の才能を秘めながらも天涯孤独で夢も希望もない日々を過ごしていた青年・才蔵は、兵衛に見出されて鍛えられ、彼の手下となる。やがて兵衛のもとに集った無頼たちは、巨大な権力に向けて暴動を仕掛ける。そんな彼らの前に、兵衛のかつての悪友・骨皮道賢率いる幕府軍が立ちはだかる。
 骨皮道賢 骨皮道賢
大泉が本格的な殺陣・アクションに初挑戦し、剣の達人である蓮田兵衛を熱演。アイドルグループ「なにわ男子」の長尾謙杜が才蔵、堤真一が骨皮道賢を演じるほか、柄本明、北村一輝、松本若菜が共演。 |
この映画には、魅力的なキャラクターがたくさん登場します。
主演の蓮田兵衛(大泉洋)、骨皮道賢(堤真一)、そして影の主人公才蔵(長尾謙杜)をはじめ、才蔵の師となる唐埼の老人(柄本明)、かつて道賢の恋人でありながら現在は兵衛の情人となっている高級遊女の芳王子(ほおうじ:松本若菜)。
 高級遊女の芳王子(松本若菜) 高級遊女の芳王子(松本若菜)
さらには、兵衛や才蔵の人間性に惹かれて集まって来る7人の勇者たち。抜刀術の天才、十尺金棒を振り回す巨漢、弓の達人の女渡来人などなど。
 弓使いの超煕(ちょひ:武田梨奈) 弓使いの超煕(ちょひ:武田梨奈)
そう・・クライマックスシーンでは、兵衛らを含めた9人の勇者が強大な道賢軍団に立ち向かうのです。
 |
|
多勢に無勢、一人またひとりと倒れていく勇者たち。これはまさに現代版『七人の侍』と言っていい。
そして、道賢側にも鎖鎌の達人や女忍者(伏士)などの腕利きが。
これは作り方によっては『南総里見八犬伝』や山田風太郎の『柳生忍法帖』、横山光輝の『伊賀の影丸』のように、オールスター対抗戦にも出来たかもしれない。
 そのくらい、一人ひとりが「キャラ立ち」しています。 そのくらい、一人ひとりが「キャラ立ち」しています。
 『八犬伝』 『八犬伝』
だが、そうはしなかった。才蔵ひとりに焦点を当てた「成長物語」、為政者の圧政と民の苦悩、そして民衆を救うスーパーヒーローとしての蓮田兵衛が軸となっています。
しかしこの映画、大方の予想を裏切って初登場7位という低調なスタートとなり、以後も勢いを挽回することはできませんでした。何故なのか?
 才蔵の成長物語 才蔵の成長物語
レビューではいくつか共通した指摘があります。その一つは台詞が「ガナリ過ぎ・何を言っているか分からない」、そして「音楽が場面に合っていない」など。
たしかに、唐埼の老人(柄本明)が才蔵に矢継ぎ早に訓練指示を与えるシーンでは字幕が無いと何を言っているか分からない(笑)ほどでした。
また、遊女の芳王子(松本若菜)が道賢に恨み事を言うシーンでは、「これNGじゃないんだ?」と思われる台詞廻しがありました。
 場面的には冷静に詰問すべきところ、感情に任せて早口でガナリ、ただのヒステリーにしか見えない。 場面的には冷静に詰問すべきところ、感情に任せて早口でガナリ、ただのヒステリーにしか見えない。
こういうのって、演出者の責任ではないかと思う。
 遊女の芳王子(松本若菜) 遊女の芳王子(松本若菜)
今回メガホンを執ってたのは『AI崩壊』や『あんのこと』を手がけた入江 悠監督。聞くところによると「あまり指示を出さないで俳優に任せるタイプ」だそう。
なので、『あんのこと』で熱演した河合優実、今回の『室町無頼』の大泉洋や堤真一のような名優が演じているシーンは非の打ちどころがなくても、全体をハンドリングする部分が不十分だったのかもしれません。(BGMの選択も含めて)
 入江 悠監督 入江 悠監督
ただ、僕が一番感じた難点は、最後に主人公蓮田兵衛を殺してしまった事。
そこに至るまでは土一揆の勝利など喝采を叫び、カタルシスを得られるシーンがあったにも関らず、最後に「親友対決」を追加し兵衛を殺してしまったことにガッカリ。
もちろん史実では、兵衛ら首謀者は捕縛されて打ち首獄門となっているのですが、せっかく時代活劇として盛り上げておいて、その後に直接対決・敗北シーンを加える必要があったのか。
同様にやって大失敗した過去作を知っています。それは1966年日本公開の西部劇『荒野の群盗』。
 『荒野の群盗』(1966年) 『荒野の群盗』(1966年)
この作品でも、主人公が妻子を殺された仇を見事討った後で、シェリフ側に立ったかつての親友と対決をして主人公が負けてエンディングでした。
後味が悪い事、この上ない。これでは他人に勧めることはできません。やはり「活劇」とバッドエンディングは相性が悪いと言わざるを得ない。
「正義は勝つ」でよかったんじゃないでしょうか。
/// end of the “cinemaアラカルト471「室町無頼」”///

(追伸)
 岸波 岸波
映画が最高潮になるのは、兵衛の秘策により土一揆の民衆が勝利し、金貸しの「証文」を焼き払って踊り狂う場面。
まるでインド映画の「突然ミュージカル」みたいに踊り出し、そして三々五々撤収して行きます。
ところがこの後、9人の勇者たちが夕陽を背景に再び町中に引き返し、道賢の大軍団に孤高の闘いを挑みます。あれ、あれ?となりました。
変でしょ? 悪徳金貸しの証文を焼き払うという所期の目的は達成してるし、大部隊に勝てないのが分かってるのに。
 夕陽を背景に9人の勇者 夕陽を背景に9人の勇者
このシーンで流れるのがまるで西部劇のような場違いBGM。まあ、カッコいいのはカッコいいんですけどね。(ヒロイズムに酔ってるだけ?)
この辺、監督も「何か説明が必要」と思わなかったんでしょうか。
 しかも僕が「蛇足」と感じた直接対決シーンは、ここからもう一度逃げた後で出て来るのでした。 しかも僕が「蛇足」と感じた直接対決シーンは、ここからもう一度逃げた後で出て来るのでした。
そんな感じなので、名優たちの演技に酔いしれながらも、「あれ?」の多い映画でした。もったいなかったんじゃないの?
では、次回の“cinemaアラカルト2”で・・・See you again !
eメールはこちらへ または habane8@yahoo.co.jp まで!
Give
the author your feedback, your comments + thoughts are always greatly appreciated.
To
be continued⇒ “cinemaアラカルト472” coming
soon!
<Back | Next>
|