小説は結構読んでいる方ですが、いわゆる文豪の名作、例えば文豪と呼ぶことに誰も異論を挟まないであろう夏目漱石の、「坊ちゃん」「三四郎」「こころ」などの長編小説は、恥ずかしながら一つも読んでいません。
自分に合った作家を探す目的もあって、最近は短編集をよく読んでいます。
文豪が書いた短編も、例えば彩図社文庫の「文豪たちが書いた」シリーズは8冊読みましたし、最近も長山靖生編「文豪と酒」「文豪と東京」「文豪と食」(いずれも中公文庫)を読みました。
 長山靖生編「文豪と酒」
長山靖生編「文豪と酒」
短編といえども気合は必要でした。
第一に、文豪と言われる方が書いたものは、概して改行が少ないのです。見開き2頁に改行が全くないこともあります。
改行や空白の1行があってこそ、リズムよく読めていると思います。「そこまで読んだら一休み」と思える改行がずっと先で、何となく読むことに疲れてしまいます。
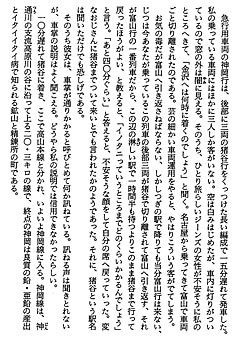 宮脇俊三「時刻表2万キロ」のケース
宮脇俊三「時刻表2万キロ」のケース
それに言行一致で口語体にはなっているものの、文語体の名残りがあるように感じる時もあります。
そして今では使わないような漢字も多用されています。
「文豪と酒」の中の梶井基次郎の「冬の蠅」には-「黝(くろ)ずんで」「紙撚(こより)」「嬉戯(きぎ)」「裘(けごろも)」「秀並み(ほなみ)」「偏頗(へんぱ)」「谿襞(たにひだ)」「劈(つんざ)く」「潦(みずたまり:本来の読みは(にわたずみ)で水たまりのこと)」・・・。

振り仮名で読めはしますが、意味の分からない語句も結構あります。読書中に辞書を紐解くことは滅多になく、結局字面を追っているだけですね。
文豪の名作を読んでいないということは、単に小説読みを騙っているだけでしょうか。
 ツーさん【2024.1.29掲載】
ツーさん【2024.1.29掲載】
 葉羽 文豪どころか50年前の小松左京や筒井康隆のSFを見直しても「改行」が少ないのに驚く。これって逆に、Web時代の現在の多改行スタイルに馴染んだから感じることかもしれない(現代の作家もそこを意識している人が少なく無いような?)。
葉羽 文豪どころか50年前の小松左京や筒井康隆のSFを見直しても「改行」が少ないのに驚く。これって逆に、Web時代の現在の多改行スタイルに馴染んだから感じることかもしれない(現代の作家もそこを意識している人が少なく無いような?)。
それと語彙・難読漢字の件だけれど、昔読んでいた小林秀雄の文章を見直すと、どうにも”上から目線”を感じてしまって共感できなくなっている。これらは「時代の流れ」がそうさせたのかもしれないね。